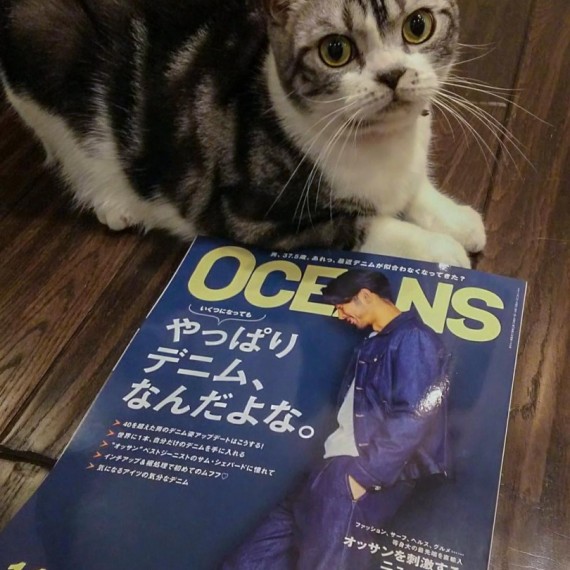ジェフ、個人的な質問で悪いが、何年か履いてちょっとくたびれてきたジーンズってどうしてる? 俺なら「シルエットが古くなったから買い替えて古い方を処分」きっとこう答えるだろう。物がダメになる以前に印象が古くなったから、とまあファッション関係者ならきっとこれが自然な感覚だと思うんだ。
ジェフ、憶えているか? 前回の徳島の職人が俺に言った「アメリカと日本では目指す物が違う」この事さ。俺は徳島の現場を見て正直、体が震えたよ。そしてハッキリ分かったんだ。ジェフ、お前も俺もヴィンテージの世界観って大好きだよな。朽ち果てる一歩手前のさ、線香花火の最後の灯りがポトリと落ちる直前に一瞬だけパッと明るくなるだろ? その瞬間と好きな世界観って何かが重なるんだよ。大切な物を愛着をもって育て、そしてダメになる瞬間にこそ最高な着心地になっている、そんなイメージさ。ジェフ、俺が訪れた徳島の工場は明治時代の創業で、基本的に生地作りの製法を変えてないんだ。もう存在自体がヴィンテージなのさ。ここが目指しているのは効率の良い大量生産ではなく、1900年来の昔気質(かたぎ)ってやつだったんだ。
その工場は広島から橋を渡って徳島へ入り、ほどなく進んだ先にある。社長から簡単なガイダンスを受けた後、工場内を案内してもらったんだ。そこで職人は語り始めたんだ。
「明治、大正、昭和、戦後と日本では庶民にまで十分な物資が行き届いていなかった。特に労働着、野良着の類いは直しては着て、直しては着てを繰り返す。そんな社会情勢を背景にこの工場は操業を続けて来た。いかに長くご愛顧頂けるかを考えて。」
そしてその言葉の意味そのものだったのが、インディゴ染めの工房だったよ。ジェフ、俺は「手作業」という言葉はこの事なんだと痛感したんだ。ここで行われているインディゴ染めの技法はかせ染めと言って、土間に穴を掘って据えた、熟成したインディゴのはいった瓶に、織り糸をつけ込む方法だ。「つけ込む」「絞る」「空気にさらす」を、ひたすら繰り返すんだ。天然インディゴは、気温などのコンディションが一定ではないのに、染め回数を調整することで、染まる色を一定にしなければならない。もうこれは経験値でしかないそうだ。天然の蓼(たで)からインディゴを生成し、吉野川の水を使い、その日の気温で作業内容を決定する。ジェフ、簡単に言うとこんな感じだ。
そして俺が注目したのが、染色中ひたすら絞り上げるという作業なんだ。「絞る」ってことでなにが起こると思う?
アメリカのデニムが効率を考えて麩菓子構造を考えた話をしただろ? 日本のかせ染めはこの「絞る」という工程で、完全に織り糸の中までインディゴを浸透させるんだ。中の中までネイビー色さ。例えるなら、あの黒糖を揚げたかりんとうだ。麩菓子とかりんとう、見た目は同じ黒糖色だが割ってみると全然違うだろ? ここで初めてあの言葉の意味が分かってくるのさ。
「アメリカと日本では目指す物が違う。」
次回、ヴィンテージな物作りと日本の目指す物、麩菓子とかりんとうについてもう少し語らせてくれ。
ジェフ、最初に、ジーンズがくたびれてたらどうする?ってお前に聞いたが、よくよく考えてみれば俺とお前が出会って30年、お前は全く同じ品番のジーンズ1種類しか穿いてなかったんだな。愚問だったよ。 じゃあまた。
※Episode 4は、こちらで次週公開予定です。