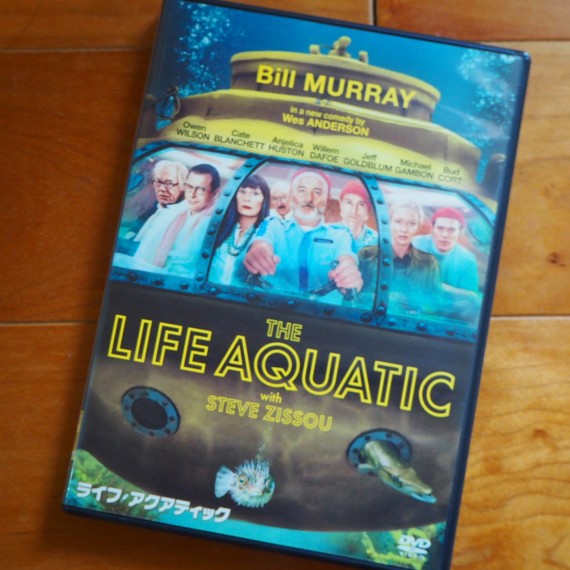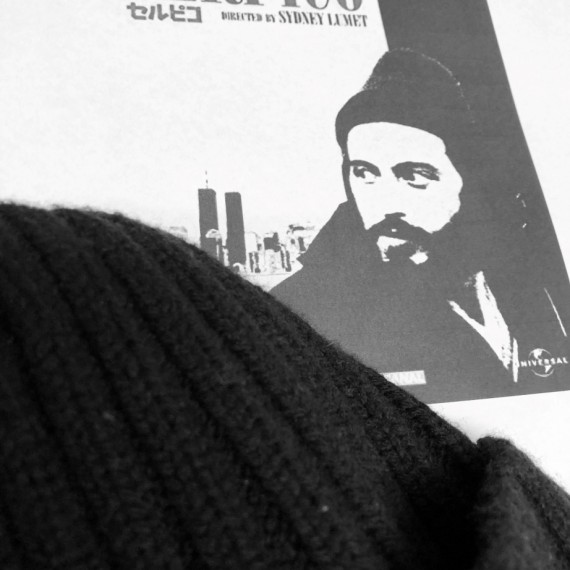映画といえば、ストーリーやテーマ、ファッションが見どころでは勿論あるのだが、一方で映画音楽という視点もある。映画音楽といえば、クラシックなところでフェリーニ作品をはじめ「太陽がいっぱい」や「ゴッドファーザー」のテーマが印象的なニーノ・ロータ、「シャレード」「ひまわり」他、刑事コロンボシリーズで知られるヘンリー・マンシーニ、「ニューシネマパラダイス」などの感動作以外にもマカロニ・ウェスタンからパゾリーニの問題作「ソドムの市」まで幅広く手がけたエンニオ・モリコーネ、日本国内では北野武やジブリ作品の久石譲といったところか。しかしながら、ヌーヴェルヴァーグを愛する諸兄にとってやはりハズせないのは、ミシェル・ルグランだろう。ゴダールの初期作品やクロード・ルルーシュの「愛と哀しみのボレロ」他、ウィリアム・クライン「ポリー・マグーお前は誰だ」や、ロバート・アルトマン「プレタポルテ」など、ファッショナブルな作品へも楽曲を提供している。極め付きは、「シェルブールの雨傘」「ロシュフォールの恋人たち」という、ジャック・ドゥミ監督によるミュージカル映画の金字塔を彩るスコア群に尽きる。特に後者のラスト近く、3つのラブストーリーが交錯するシーンで合わさる、まるで壮大な組曲のようなオーケストレーションからは、ほとんど気が触れているとしか思えない狂気すら感じてしまう。作曲家、ジャズピアニストの肩書きを持つミシェル・ルグランだが、(僕の知る限り)一度だけ俳優として映画に出演している。アニエス・ヴァルダによる「5時から7時までのクレオ」だ。劇中でもピアニスト役として一曲披露している若き日の彼、ルックスがカッコいいのだ。ブロウタイプの眼鏡、半袖のオープンカラーシャツ、リーゼント気味に後ろへ流した髪、まるでジェームス・ディーンのようで完全にアメリカかぶれ。1950~60年代において戦勝国アメリカに憧れ、かぶれていたのは日本人だけではなかった。パリの街中を疾走する手持ちカメラとジャズ。ヌーヴェルヴァーグ時代にフランスが培ったこのアメリカかぶれ感は、その後 Marcel Lassance や Maison KITSUNE、Editions M.R へと受け継がれてゆく。
REVIEW

手元で馴染んだオーダー品
「オーダーしたからこそ馴染んだ」と思えたもの、そんなモノが男にはある。AMVERが選んだオーダー品はどんなものなのか。
Read More
着られない服
買ったけれど着ない服、いまとなっては着ない服、袖を通すことができない服……。1900年初頭にフランスで作られたリネンシャツ、Trout manのシャンブレーシャツ、貴重なポパイのTシャツなど、AMVARたちの「着られない服」。
Read More
雨の日のスタイル
90年代のゴムバンド Swatch、織り糸に水を弾く機能を持たせたエピックナイロンのシリーズ、ウィリス&ガイガーのブッシュポプリン製サファリジャケット……AMVARたちの雨の日のスタイル
Read More
春のセットアップ
80年代リバイバルのアルマーニのスーツ、春の曇天にはぴったりな“グレージュ”、そしてデニム。AMVERたちが手にした春のセットアップ。
Read More