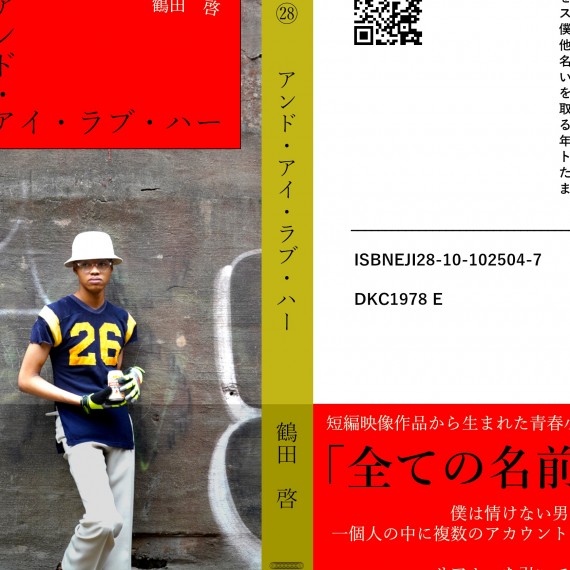話は変わるが、スーツを着るときに「~ねばならない」ことが何と多いのか、と辟易することがある。日本はよりその傾向が強い国だと思う。上襟は肩から首にかけて綺麗にのぼらなければならないし、ツキジワは入ってはいけない。ジャケットの袖口からシャツはこれくらい見えていないといけない…などなど。勿論、理解できる。完成美として。仕立屋もそこを目指して研鑽を積む。それはそれで美しいと思う。だが、それが「絶対」だとは僕にはどうしても思えないのだ。そうでなければ、映画「パリ、テキサス」('84)のスーツスタイルの格好良さをどのように説明するのか。
話は変わるが、スーツを着るときに「~ねばならない」ことが何と多いのか、と辟易することがある。日本はよりその傾向が強い国だと思う。上襟は肩から首にかけて綺麗にのぼらなければならないし、ツキジワは入ってはいけない。ジャケットの袖口からシャツはこれくらい見えていないといけない…などなど。勿論、理解できる。完成美として。仕立屋もそこを目指して研鑽を積む。それはそれで美しいと思う。だが、それが「絶対」だとは僕にはどうしても思えないのだ。そうでなければ、映画「パリ、テキサス」('84)のスーツスタイルの格好良さをどのように説明するのか。 3つボタンスーツを着る場合、上着のボタンは上2つをかける。段返りであれば真ん中ひとつだけをかける。これは常識。黄金期のハリウッドが誇るウェルドレッサー・Cary Grantは、昔観たとある1本の映画の中でシーンによって3つボタンジャケットの「上2つがけ」「中ひとつがけ」「下ひとつがけ(これは他の映画でも彼はよくやっていた)」の3種類を披露していた。その映画のタイトルは失念してしまったが…「泥棒成金」('55)だったか…。ともかく、下のボタンをかけてシワの寄った上着のシルエットを楽しむほどに、彼は随分と洒落ていたのだと思う。
3つボタンスーツを着る場合、上着のボタンは上2つをかける。段返りであれば真ん中ひとつだけをかける。これは常識。黄金期のハリウッドが誇るウェルドレッサー・Cary Grantは、昔観たとある1本の映画の中でシーンによって3つボタンジャケットの「上2つがけ」「中ひとつがけ」「下ひとつがけ(これは他の映画でも彼はよくやっていた)」の3種類を披露していた。その映画のタイトルは失念してしまったが…「泥棒成金」('55)だったか…。ともかく、下のボタンをかけてシワの寄った上着のシルエットを楽しむほどに、彼は随分と洒落ていたのだと思う。 2010年4月13日。8ヶ月間もの闘病生活を経て紀伊国屋ホールの高座に(紋付き袴ではなく)スリーピースのスーツを着て現れた立川流家元・立川談志は、3つボタンの上着の「下2つ」をかけていた。「すっかり痩せちまったから、40年前のスーツを着られるようになった」と話し、披露した演目は「首提灯」だった。声はろくに出ていなかったし、おそらく体力は限界だったのであろう。それでも僕を含め客席で観ていた者はみな胸を熱くした。あのプライドの高い家元が生身の芸に執着しようともがく姿は、まさしく「業の肯定」であった。「不完全な」噺を終えたあと、いつも通り深々と客席にお辞儀をした談志は、バツが悪いような、いたずらっ子のような何とも言えない表情で、ニヤリと笑った。長い間、理論と感性の両面から古典落語に挑み続けた立川流家元・立川談志は2011年11月21日、喉頭癌のため亡くなった。
2010年4月13日。8ヶ月間もの闘病生活を経て紀伊国屋ホールの高座に(紋付き袴ではなく)スリーピースのスーツを着て現れた立川流家元・立川談志は、3つボタンの上着の「下2つ」をかけていた。「すっかり痩せちまったから、40年前のスーツを着られるようになった」と話し、披露した演目は「首提灯」だった。声はろくに出ていなかったし、おそらく体力は限界だったのであろう。それでも僕を含め客席で観ていた者はみな胸を熱くした。あのプライドの高い家元が生身の芸に執着しようともがく姿は、まさしく「業の肯定」であった。「不完全な」噺を終えたあと、いつも通り深々と客席にお辞儀をした談志は、バツが悪いような、いたずらっ子のような何とも言えない表情で、ニヤリと笑った。長い間、理論と感性の両面から古典落語に挑み続けた立川流家元・立川談志は2011年11月21日、喉頭癌のため亡くなった。立川談志の思い出に寄せて。
2018年11月21日。