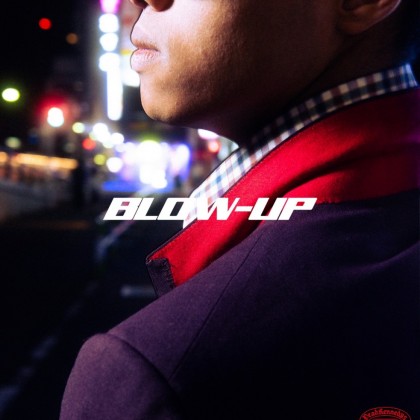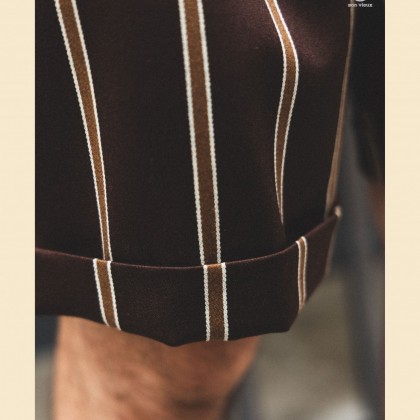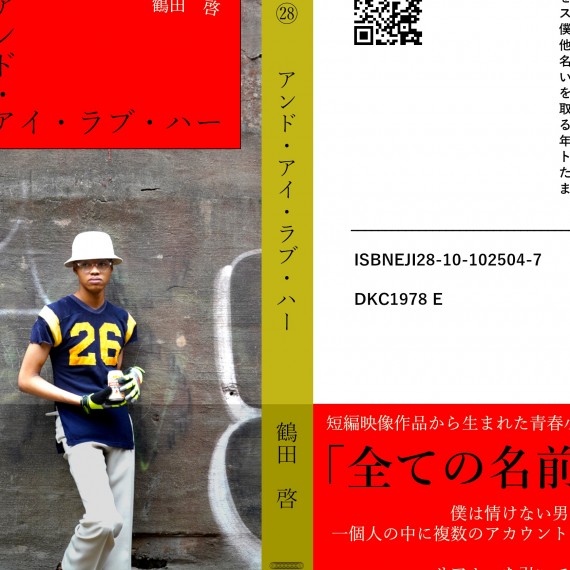数週間ほど前、ほぼ1年ぶりくらいに劇場へ足を運んだ。なんとなく映画全般(サブスク含む)を断(た)っていた、なーんにも観ていない、観ようと思えない時期、からの「PERFECT DAYS」。封切りからは半年以上が経っていた。日本が舞台だし、話題作だし、受賞もあったし、当然のように僕の周りにも鑑賞者が多かった。本当に多かった。「観ました?」と友人・知人に尋ねられて、「や、観てない」と何度答えたことか。とにかく、みんなが口を揃えて「素晴らしかった」「よかった」と言っていた気がする。
吉祥寺・UP LINKで鑑賞後、僕の感想を端的に述べるならばやはり「素晴らしかった」となる。ラストシーン、本編中もっとも大きな音量でカーステレオから流れるニーナ・シモンの曲に合わせ、長回しカットの中で役所広司が見せる表情の移ろいは最大の見せ場でもあり、実際に素晴らしかったと思う。これはたしかにカンヌの男優賞受賞に値する演技だと思った。その一方で、僕よりも先にこの作品を鑑賞した人々の感想が、ちょっと気になったのでここに記しておく。
大きく分けると周りの評価は真っ二つに割れていた。
①「平山さんのように淡々と、慎ましく、丁寧に毎日を生きていけたなら」と思った。
②「こんなふうに生きていけたなら」というコピー自体がそもそも気に食わない。制作者はユニクロの次男だし、共同脚本は電通だし、ヴェンダースは大監督だし、金持ちがブルーカラーの清貧をむやみに礼賛する上から目線の映画だ。
友人・知人の口から事前に聞こえてきた、そんな感想(圧倒的に①派が多かった)を心の片隅に置きながらも、ほぼ無心で本作に臨んだ結果、実際の鑑賞後に僕の心に残った思考は以下③のようなものだった。
③本作を象徴するキャッチコピー、「こんなふうに生きていけたなら」というパワーワードをどのようなものだと皆は感じているのだろう?
①派の人々にとっては、もしかすると「多忙な日常に疲れ果て、多すぎる情報に我を見失い、先の見えない漠然とした不安に囲まれて暗澹たる気持ちに落ち込んでしまいがちな自分に救いを与えてくれる、癒しの言葉」かもしれない。自分自身の疲弊にこの救済の言葉を重ね合わせれば、「あぁ、こういう生き方もできるんだ。現実に囚われる必要はない、僕も私も平山さんのように生きていけたなら」と即座に着地することもできる。逆に、その感動の安易さを告発するのが②の人々である。大金持ちが用意した情弱な人々向けのコピーに簡単に乗せられてしまうから、貧乏人はいつまでたっても搾取される側、つまり貧乏人のままなんだ。もっと社会の仕組みを学ばないと這い上がることもできないぞ、といったところだろうか。彼らは言うだろう。平山のように生きることなんて、実際には不可能だ。と。
しかし、僕は思う。「こんなふうに生きていけたなら」というこの言葉は、他ならぬ平山自身の心象を最も表した言葉だと。彼の過去に何があったかは本編中に描かれていない。或いは、平山の過去とは元・富裕層で、しかし今さら親に合わせる顔などなく、自分自身を呪い続けずにはいられないほど身勝手なものだったのかもしれない。トイレ清掃員というブルーカラーの職務を淡々とこなしながら、休日になると趣味であるフィルムカメラや読書で心を洗っている。しかし彼は、丁寧に淡々と毎日を過ごしているのではない。そうせざるをえないのだ。トイレをピカピカに磨き上げることでしか自分自身を浄化できないのだ。彼は清貧(=無理に富を求めようとはせず、行いが清らかで貧しい生活に安んじていること)の人ではない。むしろ、情けなく汚れまくった過去の自分自身をなかなか認めてあげることができない凡人なのだ。実際に、物語の後半で平山の心は乱れ散らかっている。ちっとも穏やかではない。スナックのママへの情念も、妹親子の登場が引き金となって甦る過去への逡巡も、規則正しいルーティンを投げ出してしまうほどに平山の心をかき乱してくる。柄本時生演じる同僚のドロップアウトは過去の自分自身を思い出させるのだろうか、明らかにイラついている。結局、彼はちっとも達観できていない。つまり(どんな過去があったにせよ)「おんぼろアパートに住み、トイレ清掃の仕事で公共に奉仕し、富を求めずつつましやかに生きていく」ことで自分自身の黒歴史を無理矢理に浄化することを選んだ凡人なのだ。姪っ子・ニコとの会話にある「今度は今度、今は今」という言葉からも平山の過去への固執が感じられる。「今度(未来)、今(現在)」と口にしながらも「むかし(過去)」を決して持ち出さない。「むかしはむかし、今は今」と言い放つことのできない重たさが、「今度は今度、今は今」という呪文に込められているのだろうか?つまり、まさに平山こそがルー・リードの「PERFECT DAYS」を聴きながら「(過去を超えて)こんなふうに生きていけたなら」と願っている張本人、「ささやかな毎日」という清廉に爪の先を引っかけてでもいいから触れていなければ奈落の底まで落ち込んでしまいそうなほどに情弱の凡人である。平山を(自分とは違う)清貧の僧侶と他人扱いした瞬間から、この映画は見えなくなる。この世にうらやましさの対象になるような人間など存在しない。だからこそ、これは僕らの映画なのだ。平山は僕である。平山は柄本時生であり、平山はアオイヤマダであり、平山はヴィム・ヴェンダースであり、平山は柳井康治である。平山はチャラ男であり、ガールズバー店員であり、映画監督であり、大金持ちの息子である。みんな、爪の先で引っかかっている。
繰り返しになるが、平山は(僕らがそうであるように)なにひとつ達観などしていない。物語の終盤に登場する三浦友和が発するセリフ=「分からないことだらけだな。けっきょく分からないまま終わっちゃうんだなぁ」は、そのまま平山の人生にも当てはまるのだろう。見事に動揺している。「何も変わらないなんて、そんな馬鹿なことあってたまるか!」と心乱れるのは図星の証である。2008年に黒沢清監督「トウキョウソナタ」内で役所広司が演じた強盗の名セリフ「俺には何も見えない!」を思わず想起してしまうような瞬間だった。三浦に分からないものが平山にだけ分かるはずがない。つまり、僕らに分からないものが平山にだけ分かるはずがない。「『こんな風に生きていけたなら』無責任な自分も少しは変わることができるかな?と思ったので、心機一転、トイレ清掃員としてつつましやかに生きてはみたけれど、それでも何ひとつ変わらない。ただ、それでも生きていくしかない」という映画こそが「PERFECT DAYS」の本質である。だから、僕は平山の生き方がちっともうらやましくない。なぜなら自分自身と同じだから。そういった意味で、電通が作ったと思われるコピー「こんな風に生きていけたなら」の意図が僕の感想を左右することは一切ない。むしろ、その意図や図式に振り回された結果、意見が2種類にしか分かれないことの方が不幸であり、それは現代社会の構造が生み出す想定内のど真ん中の分断でもある。なぜならば、映画作品そのものは出資者や製作者・監督のものであるが、(映画に限らず)あらゆる作品に対する感想は鑑賞者が個人的に所有するべきものだからだ。(個人的に)長い長い映画断ちを経て約1年ぶりに観た映画作品がこの作品で本当に良かった。外野のノイズに妨げられることなく、心の奥の隅々まで素直に染み渡った作品だった。そして、ラストシーン。カーステレオから流れるニーナ・シモン「feeling good」を聴きながら、日の出の光を浴びる平山。
Oh, freedom is mine, and I know how I feel.(ああ、自由をやっと掴んだわ、そしてこの気持ちを噛み締めるの)
It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me.(夜が明けて、新しい一日が始まる、私の新しい人生)
And I’m feelin‘ good.(最高の気分だわ)
この歌詞もまた、平山の願いである。そう信じたい、という願い。もしも平山がすでに新たな人生を始め、自由を掴み取ったと実感しているのだとしたら、ラストシーンで役所広司が見せた演技はあれほど複雑な感情のレイヤーになるわけがない。「何一つ許すことができない過去」と「分からないまま終わっていくのであろう未来」が様々な形で胸に去来しては混然一体となり、それでもアイムフィーリング、現在進行形で「最高の気分だ」と笑ってしまうしかない瞬間の中心を力強く貫くような演技だった。僕も、心の中でアイムフィーリング、大きな拍手喝采を送らずにはいられなかった。平山の影と僕の影が重なり、少しだけ濃くなった瞬間だった。