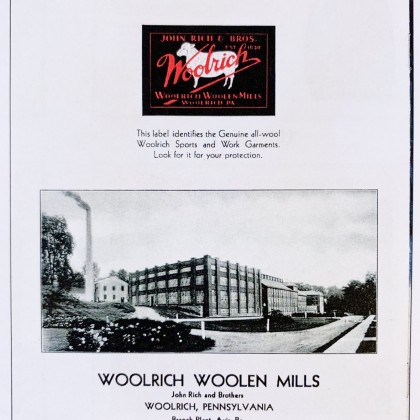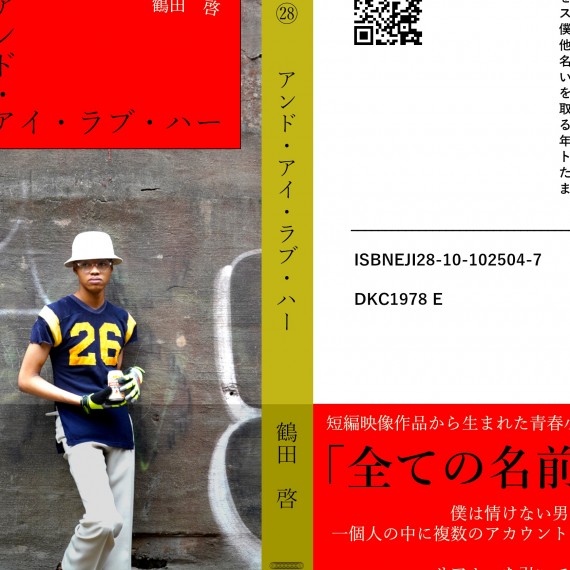「熊本で見る雪、原宿で見る雪、銀座で見る雪、札幌で見る雪、外苑前で見る雪。街が変われば、どの雪も違うように見えるけれど、今夜自宅最寄り駅前で見た雪は、なぜか子供の頃に見た雪と同じ白さに思えて、そこに少しだけブルーな鼻唄が混じった。明日になれば灰色のアスファルトが顔を出すだろう不安定な足元から目を逸らすように空を見上げ、昨夜たしかあの辺りにいたはずの鎌のように鋭くメタリックに光る三日月を深い藍色の中に探したが、それはもうどこにも見当たらなかった。こんばんは」
「熊本で見る雪、原宿で見る雪、銀座で見る雪、札幌で見る雪、外苑前で見る雪。街が変われば、どの雪も違うように見えるけれど、今夜自宅最寄り駅前で見た雪は、なぜか子供の頃に見た雪と同じ白さに思えて、そこに少しだけブルーな鼻唄が混じった。明日になれば灰色のアスファルトが顔を出すだろう不安定な足元から目を逸らすように空を見上げ、昨夜たしかあの辺りにいたはずの鎌のように鋭くメタリックに光る三日月を深い藍色の中に探したが、それはもうどこにも見当たらなかった。こんばんは」
2022年の初めに都心で降った大雪。その夜、僕は携帯で撮った街路樹の写真に添えて上記のような文章を書き散らかしていた。自分が酔っぱらっていたのかどうかも覚えていない。しかし、この写真とテキストの中にはその夜の自分が生々しくパッケージされている。
写真に記録装置としての機能があることは当たり前なんだけど、文章にもやはり同じ側面がある。それは論説・評論などの「説明的文章」とも、詩や小説・随筆などの「文学的文章」とも異なる性質に分類される「個人的文章」が果たす機能。つまりそれは日記や手紙・メモなどが記録する事象を指す。本来、それらは赤の他人に見られることのない前提で書かれたものであるはずなのだが、15年前にTwitterが登場して以来、個人的記録の為の文章が人目に触れる場でも「つぶやき」「備忘録」として横行しているのは周知のとおり。かく言う僕も、上記のような写真+テキストをオンライン上にアップしているわけなので、それがいいとか悪いとか、そんなことは今さら1㎜も思わない。言わば時代そのものなのだろう。
只、僕がこのようなテーマをコラムにして書こうと思ったきっかけはたしかに存在しており、それは写真家・大和田良氏の著作「宣言下日誌」、この本を読んだときだったと思う。2020年2月27日からのテキストと写真で始まるこの日誌は同年の7月28日でその頁を閉じるまでの間に大和田氏の中で揺れ動いた感情や日常を鮮明に記録している。古くからの友人が飯田橋に開業したギャラリーのこけら落としとして開催した、書籍と同名の写真展を訪れた僕は会場に展示されていた大和田氏の写真に魅せられて、まるでストーンローゼスのポートレイトのような色彩(実際は全然違うかもしれない)で精悍な馬の表情を写した作品を思わず購入した。その日に持ち帰った「宣言下日誌」に読み耽りながら、同氏による写真そのものの美しさと、日誌テキストの巧みさに改めて愕然とした。緊急事態宣言下の日々を切り取った写真と日常の記録は日誌としての形態を取りながらも格別に美しく、もはやこれは記録のための「個人的文章」ではなく、私小説にも近い目線で風景や肌感覚を切り取ったようにも思えて、安直なSNSでのつぶやきに逃避している自らを嫌悪すらした。緊急事態宣言下、僕は僕なりにヘボい写真やテキストをSNSに手帳に残してきただけに、なおさらその差は歴然としたものであるように感じた。翻って、自分にしか出来ないことは何だ。とりわけ、自らに芸術性を課しているわけではない。アーティストの仲間入りをしたいわけでもない。自分を立派に見せたいわけでもない。それでも、と。 「赤い衝動」
「赤い衝動」
このような経験をしたにも関わらず、今も僕は日常的に写真を撮り、その時々の心情を文字に起こす。絶対的な敗北感にまみれた自分自身を記録する。少なくとも、この生々しさからは逃げないつもりでいたいだけなのかもしれない。 「支えているのか 閉じ込めているのか 階段の柵 どっちもか」
「支えているのか 閉じ込めているのか 階段の柵 どっちもか」
そういえば、あれは3~4年前のことだったか。冬のローマへひとり、旅をした。翌朝(というか、このあとすぐ)、午前3時に起床してローマのフィウミチーノ空港へ4時半に到着→そのままパリへフライトする前夜。仮眠も中途半端に思えた僕は2時頃からホテルのベッドの上で荷造りをしながらこの旅で撮ったカメラの写真を見返していた。ふと、バチカン市内で通りすがりの観光客に撮ってもらった写真の中にいる自分自身の姿に目が留まった。いつの間にか僕は涙が止まらなくなっていた。数時間前に撮られたその写真。そこに写る自分の姿が「もうこの世には存在しない(まるで遺影のような)過去に固定された只の物体」に思え、親しい人たちに2度と会うことが出来ないという強迫観念に襲われたのだ。言い様のない哀しみと虚無が全身を貫き、現世にさよならを告げる死の感触に沈んだ。こんなことを言うと、自分が過剰にナイーブな奴であり、達観とか修行が足りない只の阿呆を率先してアピールするようで、なんとも情けない気分になってくるのだけれど。
 「家着のTシャツの上にストライプのジャケットを羽織り、少し汗ばむくらいの陽気に誘われてママチャリを漕ぐ。ホントは空と海が見たかったのだけれど、海は無理だから北北西に進路を取り、荒川へ」
「家着のTシャツの上にストライプのジャケットを羽織り、少し汗ばむくらいの陽気に誘われてママチャリを漕ぐ。ホントは空と海が見たかったのだけれど、海は無理だから北北西に進路を取り、荒川へ」
過去の写真と現在の自分。その間に横たわる時間が20年であれ3年であれ数時間であれ、そこには絶対的に不可逆な時の流れがあり、その中で人間は皆平等にゆっくりと死に向かっている。しかし、その恐るべき事実に対峙しながら自覚的に毎日を生きる人間はごく少ない。大概は夢の中にいるような気分で、鮮明に思い出せる出来事は重ねる年月に反比例して少なくなっていく。過去の出来事の集積が現在の自分を作り上げ、現在の自分の行動が未来を作り上げるのだとしても、その現在すらもあっという間に忘却の彼方へと過ぎ去ってしまう。高速道路を走る車の窓からフッと落としてしまったガムの包み紙。遥か後方へ吹っ飛んでいく紙切れの行方に気を取られる暇もなく、次のインターチェンジでハイウェイを降りるかどうかを判断しながら現在と咄嗟に向き合うスピード。只、それを繰り返していく。 「透明なビルの下 力強く黄色い路線」
「透明なビルの下 力強く黄色い路線」
そういえば、昔、僕はある女性から「鶴田さんの書く文章を読むと武田百合子を思い出します」と言われたことがある。たしかに、ある意味では淡々としているように思える僕の文章は、自己陶酔と観察眼との間に薄氷を挟んだような脆いシロモノなのかもしれない。勿論、こんなことをこの場で書くこと自体が厚顔無恥、僕の書き散らかしSNSと「富士日記」や「日日雑記」から放たれるおおらかな芸術性の薫りには大きな隔たりがあるのだけれど、只、人が日常を記録するという行為の根底に流れる漠然とした本能には普遍的な真実が隠されているような気にもなってくる。ヨーゼフ・ボイスの「すべての人間は芸術家である」という言葉を参照するまでもなく、すべての人間にとって「他人の行為は芸術であり、自分の行為は矮小な性(さが)である」と思う。自分自身を呪い、苦しみながら内蔵を吐き出すような気持ちで作品を産み出した太宰治やサリンジャーやランボーも、稚拙な写真や言葉で日常を飾り付ける凡人も、基本的には「人間」という枠の中でもがいている点で何一つ変わらない「純・人間」であると暫定しながら、僕は3杯目のチューハイに口を付け、いつも通りのくだらない日常に回帰し、下手な写真を撮り世迷い言を撒き散らして、今日という日をなんとか終えていく。