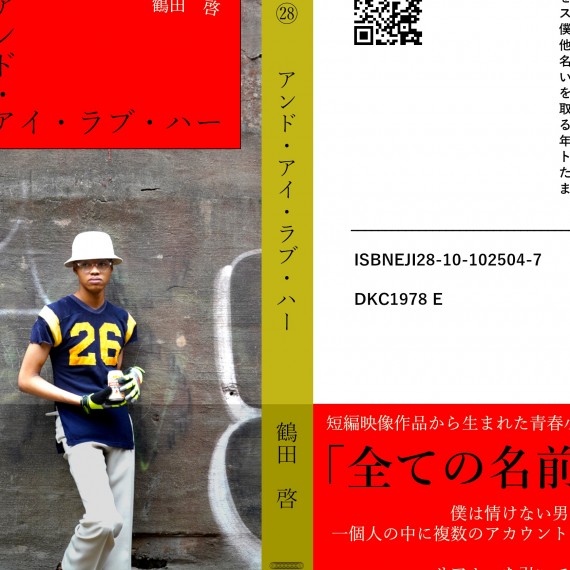紫キャベツみたいなアルパカストール、童謡「グリーングリーン」で描かれた正にその風景のように若草色をした春菊ソース、お祭りで買うラムネ瓶の如くキラキラと光る薄いブルーなMATSUDAのレンズ。そのどれもが、窓ガラスから射し込む日差しの下で輝いていた。
紫キャベツみたいなアルパカストール、童謡「グリーングリーン」で描かれた正にその風景のように若草色をした春菊ソース、お祭りで買うラムネ瓶の如くキラキラと光る薄いブルーなMATSUDAのレンズ。そのどれもが、窓ガラスから射し込む日差しの下で輝いていた。 別日。行きつけの居酒屋のホワイトボードに書いてあった「竹の子土佐煮」という文字。1年で100日以上お世話になっている店ならば、季節ものは迷わずに頼む。淡いブラウンに煮含められた竹の子の上には、薄い緑色に透き通ったふきと、白髪ネギ、かつおぶし、そして鮮やかな木の芽が乗せられていた。
別日。行きつけの居酒屋のホワイトボードに書いてあった「竹の子土佐煮」という文字。1年で100日以上お世話になっている店ならば、季節ものは迷わずに頼む。淡いブラウンに煮含められた竹の子の上には、薄い緑色に透き通ったふきと、白髪ネギ、かつおぶし、そして鮮やかな木の芽が乗せられていた。鮮やかな緑色も柔らかな茶色も香り立つ紫も同じように揺蕩う、春という季節。一寸まどろんでいるその隙に、桜の木はピンク色から黄緑色に衣を変える。この季節の尻尾は捕まえづらい。目の前に居ないと思ったその時には、後ろ姿に声が届くかどうかの距離よりも少しだけ彼方に、靄がかかったような姿でおぼろげに見えるだけ。春の始まりを前にして既に、いつかの春に輝いていた君を想う。面と向かってこんにちはと言うより先に、背中に向かってさようなら。春は、その穏やかで眠たくなるようなぽかぽかの気候に反して、他人と握手するには不向きな季節だと思う。今年の夏は、白と水色を着たい。