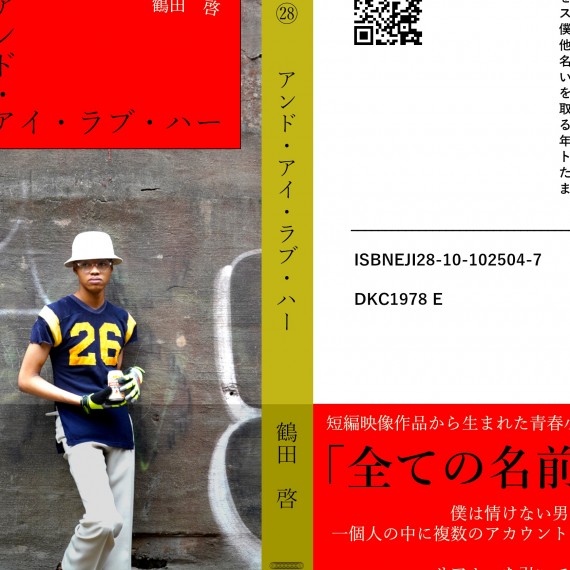アッバス・キアロスタミの映画作品に「黄桃の味」というものがある。2019年の8月に、某SNSに書き散らかした文面によると、当時の僕はこの映画に対して次のような感想を持ち、記している。
アッバス・キアロスタミの映画作品に「黄桃の味」というものがある。2019年の8月に、某SNSに書き散らかした文面によると、当時の僕はこの映画に対して次のような感想を持ち、記している。クルド出身の兵士、アフガンの神学生、自然博物館に勤務する老人。同乗者や会話の内容を変えながら、主人公の車は土と埃にまみれた、曲がりくねった道を何度も堂々巡りする(キアロスタミ作品にはしばしば、この堂々巡り、同じ道の繰り返しが出てくる)。助手席から撮った主観映像が映画の大半を占めているが、ラスト20分。主人公が車から降りて、自らの脚で駆け出していく。人に会うために。そして劇的なラストシーンへ。もしも人生にうんざりしたのならば、試しに観てみてください。あ、もちろん、してなくても。
さぁ、それから2年が経って、今の僕には「黄桃の味(英題:Taste of cherry)」がどのように感じられるのだろうか。ラストシーン直前に主人公が食べたなにげない黄桃の味の発見、その後の行動や人生観の劇的な変化。「主人公が車から降りて、自らの脚で駆け出していく」この主観を(鑑賞者本人が)どちら側に持ってくるかで、黄桃の味は如何様にも変わるものだろう。それは甘く幸せなものか。それとも酸っぱくて苦笑いするようなものか。なんてことを考えているうちに冷めてしまった串カツを一口だけ食べて、チューハイを飲んだ。