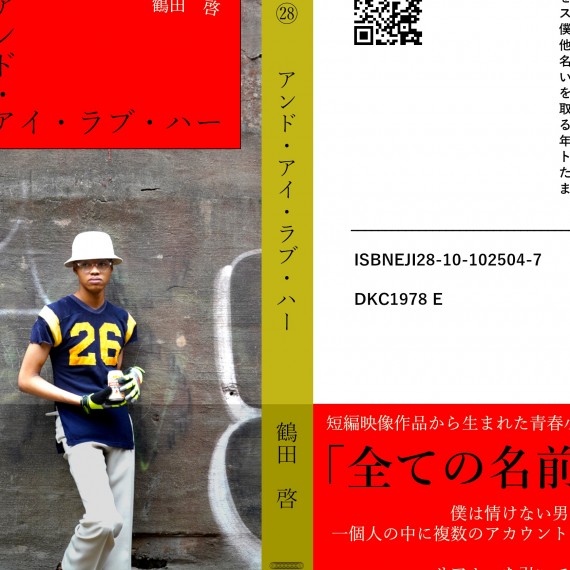ビームスのドレス部門で統括VMDを務める大島拓身(業界屈指のインフルエンサーでもある)の実兄・大島崇照(たかあき)氏は日本でも指折りの腕を持つビスポークテーラー。ビームスの同僚である弟が取り持ってくれた縁もあり、崇照氏のスーツを誂えることになったのだ。高円寺行きのバスに揺られながら、どんなものを作ろうかとぼんやり思案した結果、フッと1枚の写真を思い出した。それはアウグスト・ザンダーによる「High School Student, 1926」と題されたもので、そういえば20代の頃「いつかこんなスーツを着てみたい」と妄想していた記憶が、僕の側頭葉ニューロンを逆流しながら海馬を経由して立ち上がってきた。
 高円寺の古着屋を間借りした今回のトランクショー。初対面の崇照氏は、柔和な物腰で温かく出迎えてくれた。ひと通り自己紹介や雑談を済ませると、本題へ。件の写真を携帯の画面で見せて、僕のイメージを伝える。弟が着ていた崇照氏製作のスーツを見る限りで想像できるハウススタイルと僕の妄想を重ね合わせながら会話と採寸を繰り返し、30分ほどでオーダー完了。まだ4時前だったけど駅前の「大将」でホッピーを飲んで帰宅した。
高円寺の古着屋を間借りした今回のトランクショー。初対面の崇照氏は、柔和な物腰で温かく出迎えてくれた。ひと通り自己紹介や雑談を済ませると、本題へ。件の写真を携帯の画面で見せて、僕のイメージを伝える。弟が着ていた崇照氏製作のスーツを見る限りで想像できるハウススタイルと僕の妄想を重ね合わせながら会話と採寸を繰り返し、30分ほどでオーダー完了。まだ4時前だったけど駅前の「大将」でホッピーを飲んで帰宅した。3ヶ月後の本日、10月も終わりに差し掛かる頃、仮縫いのアポイントを目がけて再び、高円寺へ。
 Fox社のフランネルをチョイスしたスーツの原型が仕上がってきていた。さすがに3ヶ月も経つと、どのようなディテールで注文したのか、既に自分の記憶はおぼろ気なものになっている。過去にFallan&Harveyでビスポークしていた頃は、毎度ほとんど何も指定しなかったけど、今回は会話が流暢に成立する日本人同士ということもあり、珍しくあれこれとディテールを指定したのだ。というか、崇照氏が丁寧に確認しながら選ばせてくれたのだ。
Fox社のフランネルをチョイスしたスーツの原型が仕上がってきていた。さすがに3ヶ月も経つと、どのようなディテールで注文したのか、既に自分の記憶はおぼろ気なものになっている。過去にFallan&Harveyでビスポークしていた頃は、毎度ほとんど何も指定しなかったけど、今回は会話が流暢に成立する日本人同士ということもあり、珍しくあれこれとディテールを指定したのだ。というか、崇照氏が丁寧に確認しながら選ばせてくれたのだ。 記憶の糸を手繰り寄せながら、フィッティングや細部を確認する。肩パッドの量やポケットの数、パンツのウエスマン仕様は崇照氏にとっても滅多に受けない内容(僕がイメージするような全体像を注文するお客はいない、という意味)だったらしく、作っていて楽しいと言ってくれた。
記憶の糸を手繰り寄せながら、フィッティングや細部を確認する。肩パッドの量やポケットの数、パンツのウエスマン仕様は崇照氏にとっても滅多に受けない内容(僕がイメージするような全体像を注文するお客はいない、という意味)だったらしく、作っていて楽しいと言ってくれた。剥き出しになった毛芯やハ刺し、ポケットなどを型どったハンドステッチからは洋服の原始的な温かみを感じたし、2度目の仮縫いで年明けに会う約束をする「それでは、また次回」というお互いの会釈には人間らしい繋がりが溢れていた。「もう、洋服は要らない」と言う人もいるけれど、洋服を介した物語はやっぱり何時の時代も人の心を震わせる。会話とコミュニケーションを通じて、お互いに心を通わせながら、また会う約束をしながら過ごすビスポークの時間には、それがなおさら濃密に感じられる。
そういえば半年前に、自宅近所で見かけた他愛もない光景をなぜだか僕はとっさに携帯電話にメモしていた。それは次のようなものだった。
じゃあねー
ばいばーい
またあしたね
うん
また、あした、ね
自転車で走り去るふたりの男子中学生
また会うことを信じて疑わない
夕暮れの無邪気
それぞれが振り返り
もう一度だけ手を振っていた