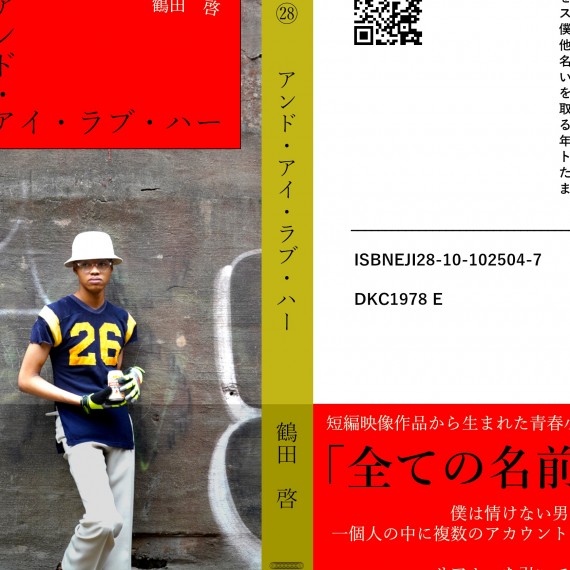2021年が開けたら、なんとなく自分の気持ちがUKファッションに傾いていることに気が付いた。「ブリティッシュ(英国風)」ではなく「UK」。この響きから実際にイメージできるファッションは1980年代にRay Petriが率いたBuffaloもそうだし、90'sニューテーラーの一角を担ったRichard Jamesによる(1998年にダスティン・ホフマンとロバート・デ・ニーロがGeorge Magazineの表紙を飾ったことで名高い)迷彩柄スーツもそうだろう。とにかく、伝統的なものや権威に対して安易に与せず、既成の美意識・価値観を徹底的に疑い、必要であれば迷わずツバを吐くアノ感じ。長いものに巻かれるよりも、もっと反抗的な力が欲しい。どうせ反抗するのなら、やっぱり英国服が着たい。どこかで僕はそう思っていたのだろうか?久しぶりにクローゼットから引っ張り出したのは英国の古参ビスポークテーラー・Kilgour French Stanburyのアイテム群だった。 1882年に創業した前身となるテーラーを母体に1937年にはKilgour French Stanburyとなり、2003年に既製服の展開をスタートした同社のコレクションを、いち早くインターナショナルギャラリー ビームスではバイイングしていたが、それは25際の僕が初めて購入した英国の高級重衣料だった。ある意味では、今の僕の原点でもある。
1882年に創業した前身となるテーラーを母体に1937年にはKilgour French Stanburyとなり、2003年に既製服の展開をスタートした同社のコレクションを、いち早くインターナショナルギャラリー ビームスではバイイングしていたが、それは25際の僕が初めて購入した英国の高級重衣料だった。ある意味では、今の僕の原点でもある。 このスーツは2004年にブランド名を変更した後のもので、Kilgourネームがついている。秋冬素材だが裏地が背抜きになっているのは(パイピング処理の美しさに自信があるので)あえて仕事を表に見せるための仕様で、軽さを演出するためだけのものではない。実際に表地や芯地はかっちりとした英国仕立てである。
このスーツは2004年にブランド名を変更した後のもので、Kilgourネームがついている。秋冬素材だが裏地が背抜きになっているのは(パイピング処理の美しさに自信があるので)あえて仕事を表に見せるための仕様で、軽さを演出するためだけのものではない。実際に表地や芯地はかっちりとした英国仕立てである。 ライトフランネルのストライプコートは2003年のもの。ネームもKilgour French Stanburyとなっている。
ライトフランネルのストライプコートは2003年のもの。ネームもKilgour French Stanburyとなっている。
10年以上ぶりに袖を通してみた。Vゾーンに合わせたのは、同じく英国のPUNKテーラー・John Pearseのターンナップカフスシャツ。サイケデリックな配色のナロータイはMichael J.Drake。いずれも15年前に買ったアイテムだ。写っていないが、足元はパープルのカラーソックスにOur Legacyのミュールを突っかけている。
 過去にエドワード・セクストンが在籍していたり、1974年にはあのトミー・ナッターがディレクターに迎えられるなど、Kilgourはサヴィルロウの中でも革新的なパターンメイキングを誇るテーラーとして知られているが、このスーツは元・1205のパウラ・ジェルバーゼが作ったらしい。彼女とは昔、何度か食事を共にする機会があった。パウラがKilgourにいたことを知っていたので、ある時このスーツを着て行ったところ「懐かしいわ、そのスーツ。私が働いていたころに作ったものね!」と喜んでくれた。彼女はセントマーチン在学中からインターンとしてKilgourでメイキングを手掛けていたが、20代前半で既にディレクターのカルロ・ブランデッリの右腕であったそうだ。5か国語を操る才女であり、1205の後はJohn Lobbのアーティスティック・ディレクターを務めた彼女らしい、早熟のエピソードである。日本文化に興味があり、音楽も好きだというパウラ。お好み焼きをつつきながら「日本のバンドでカッコいいのを教えて」と尋ねられたので、当時よく聴いていた54-71を勧めて「バンド名が記号みたいなところも1205っぽくない?」なんて話をしたことを覚えている。1Bスタイルのこのスーツは胸と腰のポケットにインバーテッドプリーツが仕込んであり、実にパウラらしい変態ミニマルなディテールだと思う。
過去にエドワード・セクストンが在籍していたり、1974年にはあのトミー・ナッターがディレクターに迎えられるなど、Kilgourはサヴィルロウの中でも革新的なパターンメイキングを誇るテーラーとして知られているが、このスーツは元・1205のパウラ・ジェルバーゼが作ったらしい。彼女とは昔、何度か食事を共にする機会があった。パウラがKilgourにいたことを知っていたので、ある時このスーツを着て行ったところ「懐かしいわ、そのスーツ。私が働いていたころに作ったものね!」と喜んでくれた。彼女はセントマーチン在学中からインターンとしてKilgourでメイキングを手掛けていたが、20代前半で既にディレクターのカルロ・ブランデッリの右腕であったそうだ。5か国語を操る才女であり、1205の後はJohn Lobbのアーティスティック・ディレクターを務めた彼女らしい、早熟のエピソードである。日本文化に興味があり、音楽も好きだというパウラ。お好み焼きをつつきながら「日本のバンドでカッコいいのを教えて」と尋ねられたので、当時よく聴いていた54-71を勧めて「バンド名が記号みたいなところも1205っぽくない?」なんて話をしたことを覚えている。1Bスタイルのこのスーツは胸と腰のポケットにインバーテッドプリーツが仕込んであり、実にパウラらしい変態ミニマルなディテールだと思う。
 そして、チョークストライプのステンカラーコート。軽い仕立てと流線型の袖パターンが当時は斬新だったが、2021年の目で見ると膝上丈が少し短く感じたので「コートではなくロングシャツだ」と思うことにして、ジャケットのインナーにレイヤード。上に羽織ったのはジョン・ガリアーノの下でモデリングを担当していたパリのデザイナー、Udo Edlingのジャケット。これもやはり2003年ごろに買ったものだ。
そして、チョークストライプのステンカラーコート。軽い仕立てと流線型の袖パターンが当時は斬新だったが、2021年の目で見ると膝上丈が少し短く感じたので「コートではなくロングシャツだ」と思うことにして、ジャケットのインナーにレイヤード。上に羽織ったのはジョン・ガリアーノの下でモデリングを担当していたパリのデザイナー、Udo Edlingのジャケット。これもやはり2003年ごろに買ったものだ。 短めのコートもジャケットのインナーに合わせれば長く見える。キャスケットは10年近く被っているJames Lock、ボトムスはAlexander McQueenのジョガーパンツとGUIDIのPL1を合わせている。
短めのコートもジャケットのインナーに合わせれば長く見える。キャスケットは10年近く被っているJames Lock、ボトムスはAlexander McQueenのジョガーパンツとGUIDIのPL1を合わせている。 昔の服に袖を通すと、自分の変化に気がつく。アイテムは変わらなくても着方が変わるということは、気分が変わったということ。時代も変わったということ。それでも変わらないのは洋服そのもののクオリティ。大人になって、目が肥えて、若いころにはまだ気づけなかったクオリティに気づくことが出来るようになると「この服に出会っておいてよかった」と心から思える。コロナ禍とともにニューノーマルがやってきて、闇雲に服を買うことは(世間一般では)減るだろう。クローゼットの中を確かめてみたときに、昔の服が当時と変わらぬ佇まいで(むしろ輝きを増して)そこにあってくれたら、それは10年ぶりに再会した旧友とすぐにでも現在の話で通じ合えるような多幸感を与えてくれる。まるで洋服の形をした友人のようだが、実際にその洋服を通じて多くの友人に巡り会えたのだから、あながち錯覚でもあるまい。「一生モノ」なんてつもりで買った服に飽きてしまうように、長く付き合うことを初めから目的にした友人関係なんてあるわけないんだけど、だからこそ結果的に手元に残ったものには嘘がないんじゃないかな。そんなことをぼんやりと考えている。
昔の服に袖を通すと、自分の変化に気がつく。アイテムは変わらなくても着方が変わるということは、気分が変わったということ。時代も変わったということ。それでも変わらないのは洋服そのもののクオリティ。大人になって、目が肥えて、若いころにはまだ気づけなかったクオリティに気づくことが出来るようになると「この服に出会っておいてよかった」と心から思える。コロナ禍とともにニューノーマルがやってきて、闇雲に服を買うことは(世間一般では)減るだろう。クローゼットの中を確かめてみたときに、昔の服が当時と変わらぬ佇まいで(むしろ輝きを増して)そこにあってくれたら、それは10年ぶりに再会した旧友とすぐにでも現在の話で通じ合えるような多幸感を与えてくれる。まるで洋服の形をした友人のようだが、実際にその洋服を通じて多くの友人に巡り会えたのだから、あながち錯覚でもあるまい。「一生モノ」なんてつもりで買った服に飽きてしまうように、長く付き合うことを初めから目的にした友人関係なんてあるわけないんだけど、だからこそ結果的に手元に残ったものには嘘がないんじゃないかな。そんなことをぼんやりと考えている。